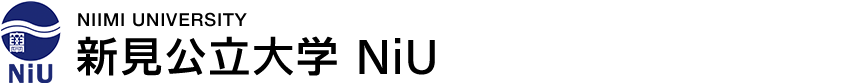【2025健康保育学科だより・第6号】人形劇の鑑賞会とワークショップを開催しました
鑑賞会とワークショップの様子
保育内容「表現」(身体表現)では、7月14日(月)2限目に、授業の一環として、岡山県倉敷市のとらまる人形劇団を招聘し、人形劇の鑑賞会とワークショップを開催しました。本講義では、人形劇の鑑賞や劇団の方とのワークショップを通じて、保育現場で必要とされる表現技術を学びます。学生たちは約50分間の非日常の世界を楽しみました。

演目「りょう太と鬼の子キバ」を鑑賞している様子

劇団の方から人形の操作技術について指導を受けている様子

健康保育学科1年生と劇団の方との記念撮影
学生の感想
人形劇を観てまず驚いたのは、たった2人で演じていたとは思えないほどのクオリティの高さです。それぞれの場面に応じて、人形の大きさや動かし方を巧みに使い分けていて、鬼の人形ひとつをとっても、手を入れて動かすタイプや棒を使って動かすタイプなど様々なバリエーションがあり、それぞれの場面に合った演出がとても印象的でした。また、1人で何役も演じる際に、声色を変えるだけでなく、演じるキャラクターの年齢や性格を考えたり、呼吸の深さを変えたりしていると訊き、表現の奥深さを知ることができました。これから自分が絵本の読み聞かせなどをする時に、教えていただいたことを意識してみようと思いました。(安田 和紗)
今回の人形劇では、演者の繊細な動きや、舞台を作るまでの入念な準備に驚きました。また、大小様々な人形達がまるで命を持ち、自らの意志を持って動いているのではと錯覚するほどなめらかで繊細な動きに心を奪われっぱなしでした。その中でもラストのシーンでは、キバと父鬼が命をかけて村を高波から守り抜くという気持ちにものすごく感動しました。さらに、舞台裏には様々な仕掛けがたくさんあり、BGMの製作や人形の種類や出すタイミングなど細かい所に力を入れているからこそ、2人という少ない人数でも迫力のある舞台になったのだと感じました。(小野 栄登)